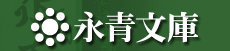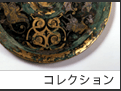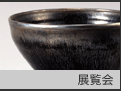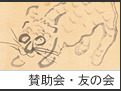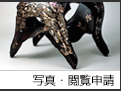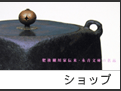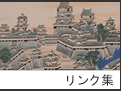※日・月曜日, 祝日(土曜日を除く)
暑い季節、扇やうちわで涼をとり、手ぬぐいで汗をぬぐう。昨今ではそんな姿も日常的ではなくなってきているものの、夏の風物であることにかわりありません。しかし、扇・うち
わ・手ぬぐいは、そうした日用品としてのみ愛用されたのではなく、様々な用途や場面で使 われてきました。
扇はその形状の豊かさから、意匠として、あるいは絵や書を書くための画面“扇面”として鑑賞の対象ともなりました。一方で、能や舞踊に扇(舞扇)は欠くことのできない道具であり、武将は軍配(軍配団扇)や軍扇で戦の指揮を執りました。
細川家は武勇の誉れ高き家柄でありながら、同時に芸術文化面にも造詣が深く、能をはじめとした道具 類・書画類が数多く遺されています。また、16代細川護立は古美術品コレクターとしてだけでなく、日本画家や洋画家たちのパトロンとして知られています。護立が日本画家らに依頼した扇もさることながら、贈答品として洋画家たちに下絵を描かせた手ぬぐいはとてもユニークなものとなっています。この展覧会は様々な用途、デザインの扇・うちわ・手ぬぐい
を見ていこうとするものです。
「幽霊図扇」鏑木清方筆(明治〜昭和時代)
「游魚図扇」横山大観筆(大正時代)
「大根と鼠」(扇面) 斎藤秋圃筆・仙_賛(江戸時代後期)
「扇を持てる女」(素描)安井曾太郎筆(昭和4年)
「団扇蒔絵大鼓胴」(江戸時代前期)
「軍配団扇」細川綱利所用(江戸時代前期)
「朝顔図団扇」堅山南風筆(昭和時代)
「西王母図」奥文鳴筆(江戸時代後期)
「雁図手拭」横山大観下絵(昭和時代初期)
 |
 |
 |
幽霊図扇
鏑木清方(1878〜1972)筆 |
西王母図(3幅対のうち)
奥文鳴(?〜1813)筆 |
雁図手拭
横山大観(1868〜1958) |
| |
| |
|